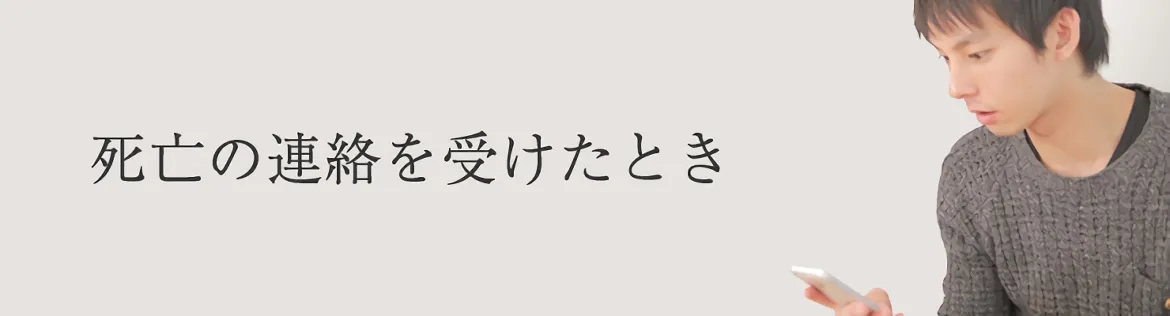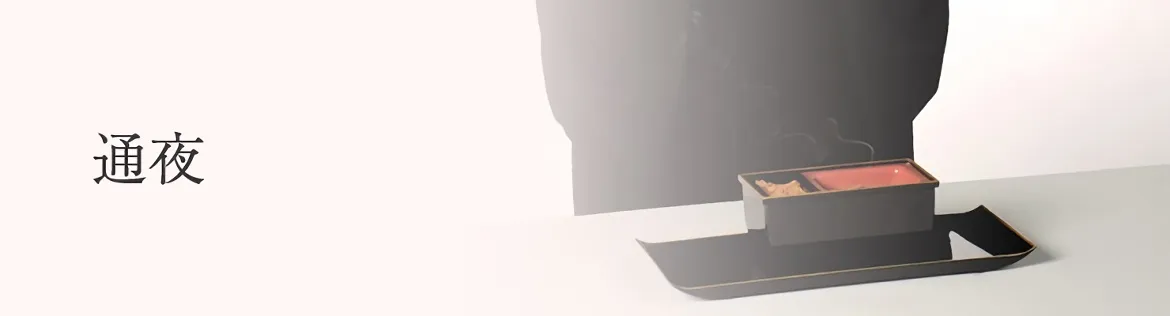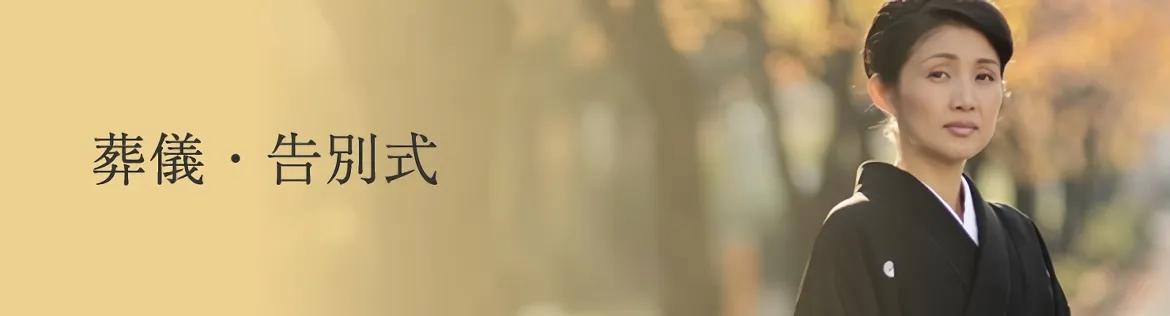参列される方
葬儀参列に際して
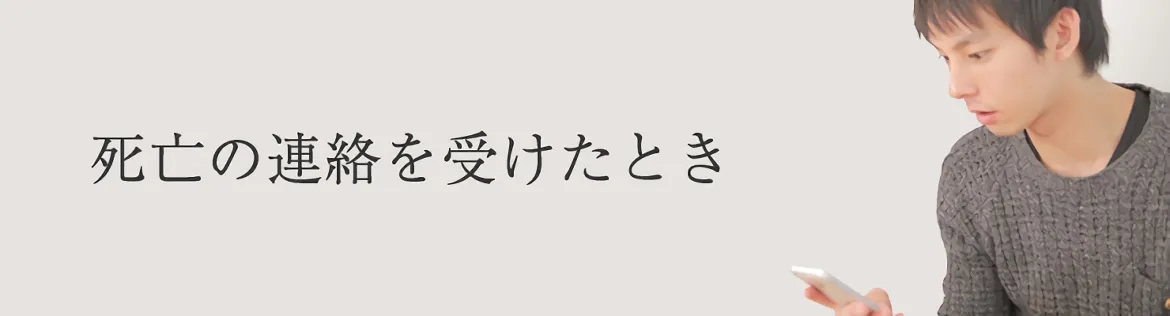
知人、近親者の訃報を受けた際に、突然のことで慌ててしまう方がほとんどです。事前に知識を身につけておくことで慌てずに対応できるようにしましょう。
人の死はいつ訪れるか誰にもわかりません。いざというときに備え準備しましょう。
近親者が亡くなった場合
- すぐに故人の元へ駆けつけましょう。急ぐことですので喪服に着替えて行く必要はありません。故人のもとに着いたらまずは遺族にお悔やみを述べましょう。そして遺族のお手伝いをしましょう。
- 性別や年齢で引き受ける役割が異なることが多いので遺族の指示に従いましょう。
引き受けることが多い役割
- 男性の場合
葬儀、お通夜の受付、式場の準備など
- 女性の場合
台所仕事、弔問客の接待など
親しい友人や知人が亡くなった場合
- 特に親しい友人(親友・幼なじみなど)の場合、連絡をもらったらすぐに駆けつけましょう。こちらも喪服ではなく平服で構いません。状況を見て人手が足りていないようなら手伝いをしましょう。
- それほど親しくない知人の場合、お通夜か葬儀どちらかに参列するようにしましょう。
- ご遺体の枕元に案内されたら、まずは線香をあげ、遺族にお悔やみの言葉を述べましょう。
- 通夜もしくは葬儀に伺うことを簡単に述べ、軽く挨拶をして速やかにその場をあとにしましょう。
ご近所の方が亡くなった場合
- 親しいお付き合いをしていた場合、すぐに駆けつけてお手伝いなどを申し出たほうがよいでしょう。
- 特に親しくない方の場合は、その日は玄関先で簡単にお悔やみを述べ、通夜か葬儀に参列する旨を伝えます。
仕事関係者の方が亡くなった場合
- 故人が同じ会社または取引先の方であった場合、一人だけ先に弔問せず、まずは会社の担当部署の方針に従いましょう。
遠方などすぐに弔問できない場合
- 様々な理由で弔問できない場合、代理人を立てる方法もあります。 代理人は弔問をする人の配偶者が基本的ですが、配偶者も弔問できない場合は家族でも良いと思います。
- 代理人を立てられない場合は、弔電だけでも打ちましょう。香典は、後日不祝儀袋に入れて現金書留で郵送しても良いです。
通夜参列に際して
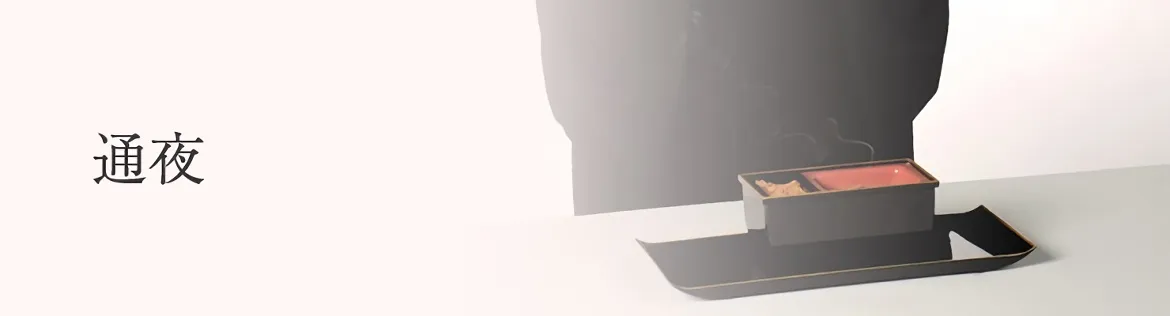
本来の通夜の意味
本来、通夜とは遺族、近親者、ごく親しい友人だけが夜通しで故人に付き添い、別れを惜しむことを意味していました。しかし近年では葬儀に参列できない人の為に、友人・知人の弔問を受ける意味合いが大きいようです。
通夜の服装
- 通夜の場合、急ぎ駆けつけたという意味をこめて喪服でなく平服でも構いません。しかし、派手な服装は避けましょう。黒や紺などの落ち着いた色の服装が基本です。
※通夜だけに参列する場合、喪服を着用していくのが良いでしょう。
香典について
- 通夜だけに参列する場合、香典は必ず持っていくようにしましょう。
- 葬儀、または両方に参列する場合、通夜参列の際にお持ちしましょう。
- 香典は袱紗(ふくさ)に包んで持っていき、まず受付に向かい、「形ばかりではございますが、ご仏前にお供えください」といって渡します。
- 金額は、故人との関係、喪家の葬儀方法や規模、弔問客の社会的地位などによっても変わります。
香典に包む金額の目安は?
香典の金額は生前の関係や等によって変わります。下記を一例として参考にしてみてください。
- 両親の場合
5~10万円
- 祖父母・叔父・叔母の場合
1万円
- 兄弟姉妹の場合
3~5万円
- 友人・知人・会社関係者の場合
5000円~1万円
通夜参列の際のマナー
- 通夜は席次が決まっていないことが大半ですので、先に入った人から奥から順に座るようにしましょう。故人との関係があまり深くない場合、弔問者が自分より年配の方が多い場合には末席(祭壇から遠い席)に座るようにします。会場の係員の指示があればそれに従うようにしましょう。
- 遺族に話しかける場合は簡潔に済ませる方が良いでしょう。遺族は、すべての弔問客に接しなくてはならないので長話は禁物です。間違っても死因を詮索したりしてはいけません。
葬儀・告別式参列に際して
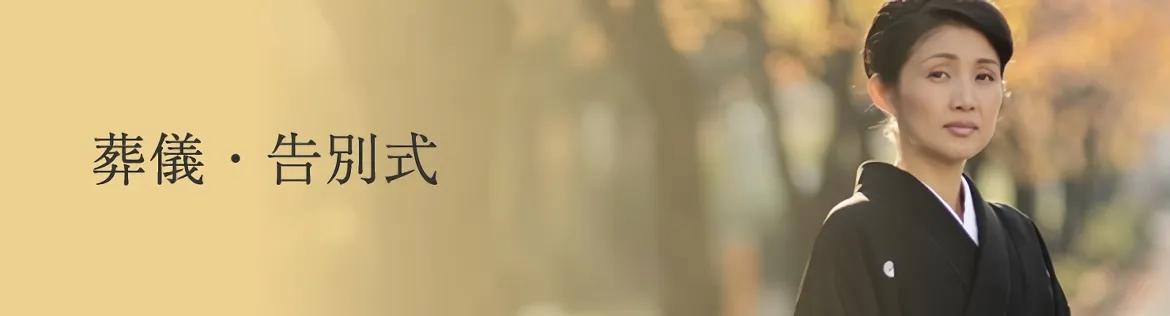
服装・持ち物
- 葬儀は礼服・喪服が基本となります。お子様は、黒や紺色の地味な服装にしましょう。
- 中学生、高校生の場合は学校の制服が礼服となります。制服がない場合は、小さなお子様同様、黒や紺色の地味な服装にしましょう。
- 数珠は忘れないようにしましょう。数珠は仏式の儀礼のみで使われるものなので、神式やキリスト教式の儀礼に持ち込むのはマナー違反です。事前に確認できるのであれば宗派など確認することをお勧めいたします。
- 女性のアクセサリーは、基本的に結婚指輪以外は身につけないようにします。身に着ける際は黒オニキスや黒真珠、白真珠などの一連のネックレスや1粒のイヤリングなどであれば問題は無いと思います。
- バッグは、なるべく光沢が無く、シンプルな落ち着いた色のものを選びましょう。ハンカチは黒か白の無地のものにしましょう。
- 香水などはなるべく使わないようにしましょう。
葬儀・告別式の参列マナー
- 受付は短い挨拶だけにします(挨拶例:「このたびはご愁傷様でございます」など)。遺族を見かけても長話はしないように心がけましょう。
- 弔辞は、故人に捧げる弔いの言葉です。弔辞を頼まれた場合は快く引き受けましょう。弔辞は遺族の手元に残るので、きちんと原稿を作る必要があります。
- 焼香は宗派により作法や回数が異なりますので注意しましょう。係員の方が教えてくれることもありますが、事前に自分でしっかりと頭に入れておくとよいでしょう。
- 僧侶が読経を行っている間は席を立ったりするのはマナー違反です。参列者が多く、椅子に座れない場合は、その場で立ったまま合掌するようにします。
香典
通夜で香典をお供えした場合は改めてお供えする必要はありません。
香典に包む金額の目安は?
香典の金額は生前の関係や等によって変わります。下記を一例として参考にしてみてください。
- 両親の場合
5~10万円
- 祖父母・叔父・叔母の場合
1万円
- 兄弟姉妹の場合
3~5万円
- 友人・知人・会社関係者の場合
5000円~1万円
出棺
- 出棺に際しては、帽子、手袋、コートなどは外し、霊柩車に合掌して見送ります。心の中でお別れの挨拶をして見送りましょう。
- 出棺の後はできるだけ速やかにその場をあとにしましょう。
お斎(おとき)
- お斎(おとき)のお誘いを受けたら、厚意を素直に受け入れ、遠慮せずに参加する方が良いでしょう。
- 食べ過ぎ、飲みすぎには注意し、静かに故人の思い出を遺族や友人・知人と語りあうようにしましょう。
Copyright © 株式会社 セレモ長岡 All Rights Reserved.